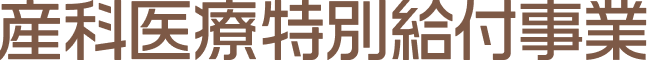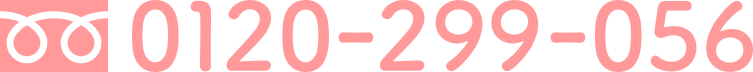事業の仕組み
運営組織<公益財団法人日本医療機能評価機構>
公益財団法人日本医療機能評価機構は、本事業の運営組織として、給付対象の認定手続き、特別給付金の支払い手続き、周知・広報等の事業運営業務を行います。
特別給付金の支払いの仕組み
児・保護者(給付申請者)が日本医療機能評価機構(運営組織)に給付申請をすると、運営組織が開催する審査委員会において給付対象の可否について審査が行われ、給付対象となった場合には、損害保険会社から直接特別給付金が支払われます。

給付の対象となる者
給付対象の3つの基準
① 出生年ごとの在胎週数・出生体重


給付対象基準は、次に定める期間中に一定の条件(在胎週数、出生体重)で出生し、脳性麻痺(※1)になった児となります。なお、在胎週数、出生体重の基準に該当しない児は、一律に給付対象外となります。
- (1)平成21年(2009年)以降平成26年(2014年)末日までに出生した児
- 在胎週数 28週以上 33週未満で出生し脳性麻痺になった児、または在胎週数33週以上かつ 2,000g未満で出生し脳性麻痺になった児
- (2)平成27年(2015年)以降令和3年(2021年)末日までに出生した児
- 在胎週数 28週以上32週未満で出生し脳性麻痺になった児、または在胎週数32週以上かつ 1,400g未満で出生し脳性麻痺になった児
② 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺
除外基準として、先天性要因および新生児期の要因による脳性麻痺に関しては、給付の対象とはなりません。なお、先天性や新生児期の要因がある場合でも、その要因が脳性麻痺の主な原因であることが明らかでないときは、給付対象となります。
- (1)先天性要因
- →両側性の広範な脳奇形、染色体異常、遺伝子異常、先天性代謝異常、先天異常
- (2)新生児期の要因
- →分娩後の感染症等
また、児が生後6か月未満に死亡した場合は、給付の対象となりません。
※「先天性要因」に示される疾患等があっても、重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、「除外基準」に該当しません。※「新生児期の要因」(感染症等)であっても、妊娠や分娩とは無関係に発症したものであることが明らかでない場合は、「除外基準」に該当しません。
③ 身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺
重症度の基準は、身体障害者障害程度等級1級または2級相当となります。
※重症度については、身体障害認定基準(身体障害者手帳の障害程度等級)を参考にして判断しますが、そのものによるのではなく、産科医療特別給付事業 給付申請用 専用診断書(給付認定申請時に必要な脳性麻に関する診断書)および診断基準によるものとなります。重度の運動障害については、「下肢・体幹」と「上肢」に分けて、それぞれの障害の程度によって基準を満たすか否かの判定を行います。
なお、「下肢・体幹の運動障害」または「上肢の運動障害」のいずれかによる障害程度の判定では重症度の基準を満たさない場合でも、下肢・体幹および上肢の両方に障害がある場合(片麻痺等)は、下肢・体幹および上肢の運動障害の総合的な判断で基準を満たすことがあります。
※「下肢・体幹」に関しては、将来実用的な歩行が不可能と考えられる状態、「上肢」に関しては、両上肢(両腕)では握る程度の簡単な動き以外ができない状態、また一上肢(いちじょうし)(片腕)では機能が全廃した状態を「重度の運動障害をきたすと推定される状態」とします。なお、「実用的な歩行」とは、「装具や歩行補助具(杖、歩行器)を使用しない状況で、立ち上がって、立位保持ができ、10メートル以上つかまらずに歩行し、さらに静止することを全てひとりでできる状態」とします。
特別給付を申請できる者の前提条件
特別給付を申請できる者の前提条件は、以下の(1)、(2)いずれも満たす者となります。
- (1)産科医療補償制度加入分娩機関と妊産婦が産科医療補償制度の補償の契約を結んだうえで、掛金相当分を支払っていること
- (2)現に産科医療補償制度の補償金を受領していないことまたは分娩機関からの損害賠償金等を 1,200万円以上受領していないこと