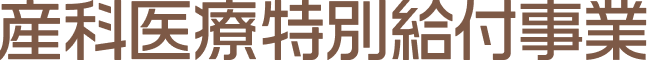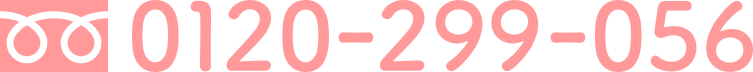Q&A
制度全般
-

本事業はどのような目的で創設されたのですか。
-

産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的としています。
-

脳性麻痺とはどのような症状なのですか。
-

胎児のときから生後1ヶ月までに起きた脳障害の後遺症で、運動発達や姿勢に異常を起こす病気です。
-

分娩機関がこの制度に加入しているかどうかは、どうやって確認できますか。
-

このホームページの「事業案内」→「加入分娩機関検索」で確認することができます。
-

給付金には所得税がかかりますか?
-

児に支払われる給付金は非課税所得となります。また、児が本事業開始時点で既に亡くなっている場合において、その児の配偶者、直系血族又は生計を一にするその他の親族に支払われる給付金についても、同様に非課税所得とされております。詳細は以下の国税庁ホームページにてご確認ください。
産科医療特別給付事業に基づき支払われる給付金の所得税法上の取扱いについて|国税庁
給付申請
-

登録証をなくしてしまいました。コピーを送ることができないのですが、どうしたらよいですか。
-

登録証を紛失または破棄されている場合は、分娩機関に妊産婦管理番号を確認のうえ、産科医療特別給付事業 給付申請書(別表第二書式)の妊産婦管理番号記入欄に妊産婦管理番号を記入してください。そのうえで、ご不明なことがある場合は運営組織にご相談ください。
-

里帰りでお産をしたので、ふたつの分娩機関から登録証をもらっています。給付申請書類として、どちらの登録証を提出すればよいですか。
-

お産をされた里帰り先の分娩機関で交付された登録証の写しを提出してください。
-

給付申請書類一式をそろえて運営組織に提出しましたが、受理通知が送られてきません。どうしたらよいですか。
-

給付申請者からすべての給付申請書類が提出され、書類に不備や不足がないことが確認できましたら、運営組織はすべての書類が運営組織に到着してから60日以内に「受理通知書」を発送します。給付申請書類提出後60日を経過していない場合は、「受理通知書」が届くのをお待ちください。60日を経過している場合は、運営組織にご確認ください。
-

分娩機関が廃院しているため、分娩機関から必要書類を取得することができません。どうしたらよいですか。
-

診療を行った際に作成される記録などについては、法律上一定期間の保存義務が課せられているものがあります。また、廃院後も引き継いだ医療機関にて診療録等が保管されている場合などがありますので、関係する医療機関等にご相談ください。
-

専用診断書ではなく、身体障害者手帳を申請するための診断書で代用できますか。
-

本事業では、重度の脳性麻痺について正確な診断を行うため、専用診断書を用いて障害程度の判定を行うこととしています。身体障害者手帳を申請するための診断書など、専用診断書以外での書類による代用はできません。お手数ですが、専門の医師が作成した専用診断書を提出してください。
-

分娩機関から文書料を請求されたのですが、どうしたらよいですか。
-

厚生労働省において定められた「産科医療特別給付事業実施要綱」において、分娩機関は、給付申請者の依頼に応じて、診療録、助産録および検査データの写し等について、運営組織に直接提出する業務を行うこととされています。
なお、必要な資料作成やコピー等にかかる文書料等は分娩機関にご負担をお願いしておりますので、その旨を分娩機関にお伝えください。 -

すでに児が亡くなっていますが、給付申請できますか。
-

生後6か月未満で亡くなった場合は、給付の対象となりません。生後6か月以降に死亡した児については、給付申請できます。
審査・給付
-

給付申請してから審査結果が分かるまで、どのくらいかかりますか。また特別給付金はいつ頃支払われるのですか。
-

受理通知を運営組織から送付した日(受理通知書の右上の日付)の翌日から原則として120日以内に、運営組織において審査を行い、審査の結果を通知します。 審査結果が「給付対象」の場合は、特別給付金申請に必要な書類一式を運営組織に送っていただきますと、すべての書類が届いてから原則として60日以内に特別給付金が支払われます。
-

分娩機関から損害賠償金等を受領しています。損害賠償金等と本事業の給付金の両方を受領することができますか。
-

給付申請者が分娩機関等からの損害賠償金等を受領する場合は調整が行われ、損害賠償金等の額が1,200万円以上の場合は給付対象外となります。また、1,200万円以下の場合は差額が支払われます。
-

特別給付金は既存の社会福祉制度における給付と調整されますか。
-

特別給付金の支給は既存の社会福祉制度に影響されません。